ふるさととは、家族とは何か『みんなのうた』重松清 感想

今回読んだのは重松清『みんなのうた』。
私にとって、初めての重松清作品でした。(多分)
重松清『みんなのうた』あらすじ
主人公は、東大受験に3浪の末失敗したレイコさん。
浪人中は東京で生活していましたが、夢破れて帰郷することになります。
レイコさんの出身は、人口が減り続けていわゆる過疎化している農村。
これまでは親の脛をかじりながら浪人生活を続けていたレイコさんですが、3年も浪人して失敗しているので、今後についても考えなければなりません。
ふるさとに戻って就職するのか、もう1年受験させてもらうのか、他の大学に志望校を変えるかなどなど。
帰郷したレイコさんがふるさとで何を思うのか、また家族や同級生はどのような人生を送るのかを覗き見ることができる作品です。
この作品の大きなテーマは、”ふるさと”と”家族”
この作品の大きなテーマは、”ふるさと”と”家族”でした。
そもそもふるさとってどのような感覚なんでしょうか。
私は生まれも育ちも東京なので、あまり"ふるさと"という感覚が身近ではありません。
田舎のイメージって
地方や田舎のコミニティってかなり狭いイメージがあります。
高校卒業後に、誰が何をしているかはみんな知っていて、情報網がすごく発達しているイメージ。
地方に住むのは私には向いていないだろうな〜なんて思っていました。
この作品に出てくる、レイコさんの地元の梅郷も、コミニティが狭く深くの地域です。
ただ、私が嫌悪感を抱きながらイメージしていた”田舎”とはちょっと違うような気がしました。
出てくる登場人物にイヤな人がいないからでしょうか。
みんな考えることがあって、地方出身ならではの悩みであるとか、地方独特の家族文化であるとか・・・。
私が今まであまり見えていなかった部分を、本作で見ることができたような気がします。
地方の世界を知る
先述した通り、私は生まれも育ちも東京ですが、親戚は地方にもいます。
私は地方にいる親戚のお家に遊びに行くたび、地方の年配の人の発言だとか行動に疑問を持つことも少なくなかったです。
時代遅れというか・・・。
男尊女卑であったり、家庭や血を存続させることに重きをおく考え方であったり、都会に住んでいる人からすると、嫌悪感を抱くようなことも多々ありました。
本作を読むことで、少しだけそのような発言をする人の背景や本意を感じることができたのは、勉強になる点でした。
本作を読んで地方もいいな、なんて思うことはできませんでしたが、あえて自分から遠ざけて交流を断つようなことはしたくないと感じました。
都会にはいろんな人がいて、それぞれみんな違うものですが、同じような地方にもいろんな人がいて、みんな違うものであると、改めて実感できた作品でした。
『みんなのうた』を読むのがおすすめの人は?
本作を読むのにおすすめなのは、高校生以上の人です。
地方出身の人や、都会出身の人、人生の岐路に立っている人などなど・・・。
とにかくいろんな人が出てきて、いろんな人の人生を垣間見ることができます。
特に高校生以上の人であれば、色々と読みながら考えさせられることがあるでしょう。
なんというか、感動する作品を読みたい!というよりは、じっくり考えながら読みたい、という人におすすめしたくなる作品でした。
気になった人はぜひ。
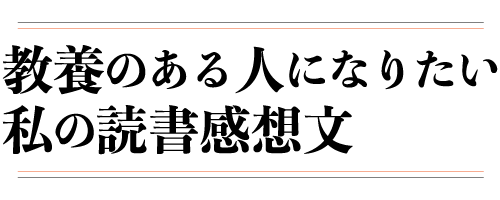

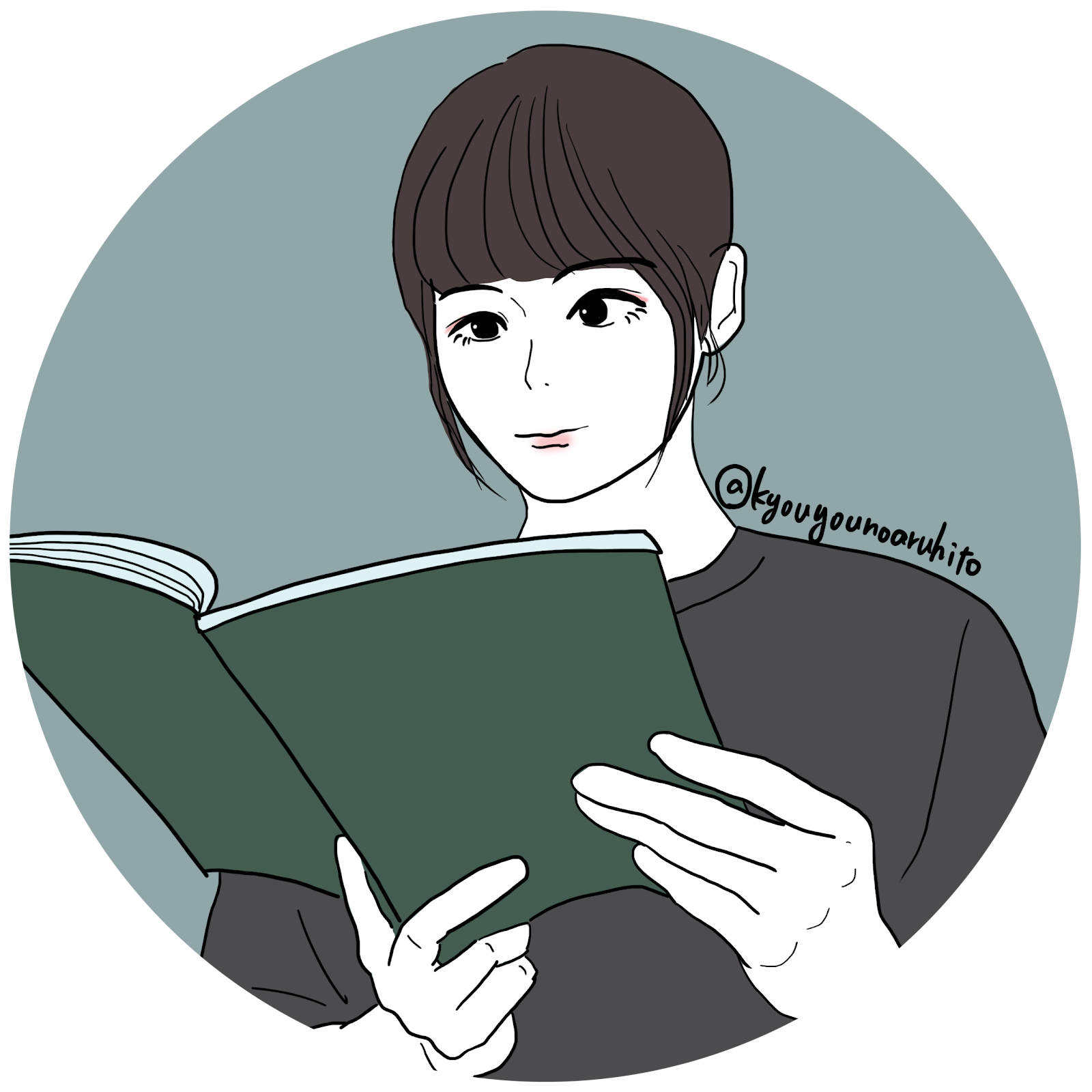 教養のある人になりたい私の読書感想文/kyouyounoaruhito
教養のある人になりたい私の読書感想文/kyouyounoaruhito


