『ひきこもりの弟だった』葦舟ナツ 感想 | タイトルからどんな結末が想像できるか
 |
| (二人の出会いのシーンをイメージして作成) |
『 ひきこもりの弟だった』は、数年前に購入して一度読み終わっていた本ですが、最近ふと読み直そうと思い、久しぶりに引っ張り出してきました。
読み直してみると、感じ方に変化を感じました。
何というか、自分が今日々の生活の中で感じている憤りを、そのまま文字に起こしてくれているような・・・。
今回の読書ではそう思いました。
では、詳しく感想を綴っていきます。
『ひきこもりの弟だった』の大まかなあらすじ
ひきこもりの兄を持つ主人公の啓太は、ある雪の降る日、千草という女性に声をかけられて結婚することになる。
啓太にひきこもりの兄がいて家族関係が良好でないのと同じように、千草にも何か抱えるものがあるようだったが、お互いに大切にすることを条件に夫婦として共同生活を始めるようになる。
共同生活を通じて、心地よい幸せを感じながらも自身の思い出したくない過去の記憶もよみがえってくる。
愛するとはどういうことかを知っていきながら、二人の生活がどのように変化していくのか。
タイトルが不思議だった
個人的にこの作品の第一印象は、「このタイトル、どういう意味なんだろう」でした。
”ひきこもりの弟だった”は、読了後は「ひきこもりの兄を持つ”弟”」だと納得しましたが、まだ当時学生だった私は様々な方向に妄想が膨らむものでした。
タイトルだけ見て、主人公がひきこもりである作品なのか、ひきこもりである弟について、客観的に見ていく作品なのかなど色々考えながら、レジに持っていった記憶があります。
家族とは、遺伝とは
主人公は、ひとり親家庭で兄がひきこもりという、なかなかに複雑な家で育ちました。
この作品には、主人公以外にも複雑な家庭環境を持つ人が出てきます。
主人公・啓太の妻となる千草もそうですし、啓太の親友の深川もそうです。
読んでいく中で、こんなにも心が嫌な意味でざわつくのは久しぶりの感覚だな、と思うくらい家族であることの苦悩が感じ取れました。
私自身も、少なからず家族に対して嫌悪感を抱くことがあります。
(この作品の登場人物ほど酷いものではありませんが・・・。)
この作品を読みながら、主人公と同じように過去を追憶していきました。
特に共感したのは、子供を作ることへの抵抗感。
自分も親や家族と同じような思想や行動をしてしまうのではないか、もし子供ができたら同じような血を増やすことになってしまうのではないか。
遺伝って、良いことも悪いことも継いでしまうからこそ、血縁に嫌悪感を抱くことがあると自身や次世代のことまで不安になってしまいます。
そんな苦悩を文字だけで表現されているこの作品は、今まで感じていたモヤモヤをくっきりハッキリと明確にしてくれました。
幸せだからこそ思い出す過去の苦い記憶
啓太と千草の夫婦生活は、当初の条件通りお互いを大切にしながら行われています。
お互いを大切にしながらの生活は、最初は他人と同居することに慣れず、ストレスを感じることもありましたが、なかなかに幸せなものでした。
ただし、啓太も千草も幸せだからこそ、過去を追憶することが多々ありました。
この作品の面白いところだなと思ったのが、お話の進め方が現在と過去を行ったり来たりしているところです。
現在の夫婦生活で穏やかなシーンを描くと、過去の苦い記憶が描かれる。
夫婦生活はたった1年ほどですが、過去の追憶は物心がついた頃から大学卒業までの長い時間です。
啓太にとっての幸せの1年は、過去の嫌な十数年に匹敵するものかな、なんて思いました。
幸せを感じると不安を感じることって、よくドラマなどでも見ますし現実の世界でもよくあることだろうと思います。
もしかしたら、結婚とか家族を作るって、幸せと不安の両方を抱えることなのかもしれないですね。
人のことを考えているようで保身に走ること
この作品で、私の中で特に強烈に印象に残ったのは、ひきこもりである兄ではなく、啓太の母親でした。
というか、全体的に女性というものの嫌な部分がよく見える描き方でした。
悲劇のヒロインになりたがったり、物事の解決を先送りにしたり。
見えないものには蓋をして、私頑張ってる、私がいないとダメなの、という感じ。
”人のことを考えているようで保身に走っている”というのは、啓太が母親に向けて感じたことでした。
身近にそういうタイプの人間がいる私は、余計に啓太や深川に共感しやすかったのかもしれません。
一方で、女性だけが嫌なふうに描かれているわけではなく、男性、というよりも父親の描かれ方も印象的でした。
言うなれば父親は「悪」みたいな存在。
誰もが幸せな家庭に生まれるわけではない、という現実をまざまざと見せつけられているようですね。
大人になるってこういうこと
人はいつか変わるタイミングがある、ということがこの作品を読んで印象に残ったことです。
これは、ネタバレになってしまうので詳しく書けないのですが、啓太が最終的に大人になったんだなと思うシーンがあります。
親友の深川にも大人になったなと感じる節目がありました。
(深川は登場時から達観しているタイプではあったと思いますが。)
一方で、ずっと変われないままだなという登場人物もいました。
この作品を読んでいると、変われるタイミングを掴めた人と、そうでない人では、後者の方が本当の意味で不幸なんだろうな、と感じました。
私はまだ、この主人公のように大人になれていないのかもしれません。
なぜなら、最後のシーンで私は、「ああ、啓太もそういうふうになったんだ」と理解はするけど納得はできない・・・みたいな感覚になったから。
皆さんは、この結末を読んでどのように感じましたか?
学生の頃と社会人の今、感じ方の違い
前回読んだのは学生の時だったので、わりかし今よりもサラッと読んでいた気がします。
社会人になって、家族の今まで見えていなかった部分を知り読んでいる今は、もっと心の揺さぶられ方が大きく感じます。
何というか読んでいて苦しくなる感じ。
昔に比べると、自問自答しながら読むことになりました。
主人公と年齢が近いからなのか、自分が変わってしまったのか、家族が変わってしまったのか・・・・。
多分結婚して子供が生まれてから読むと、また感じ方が変わりそうです。
気になった方はぜひ。
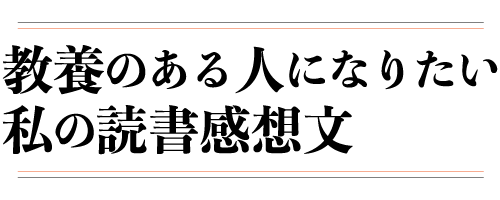

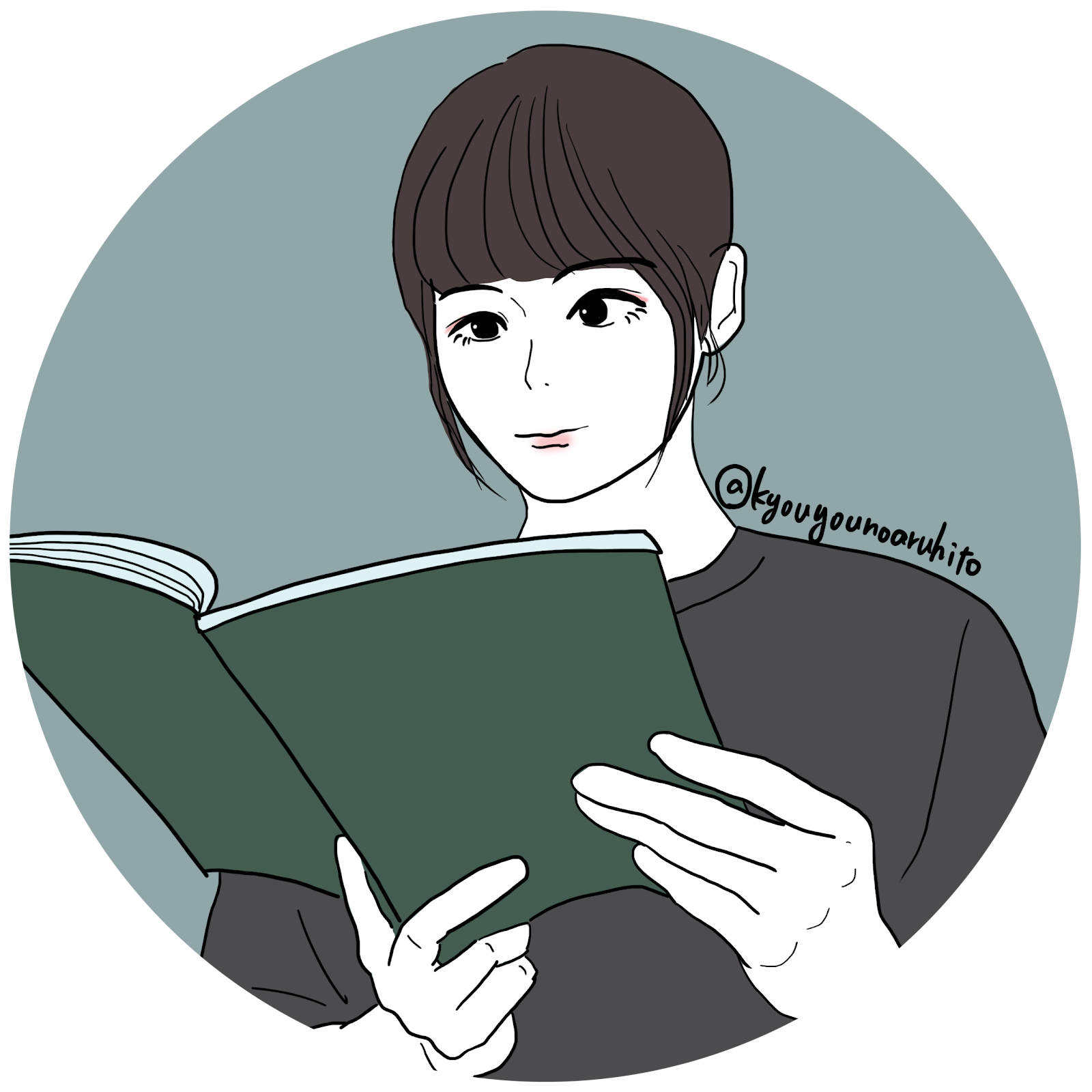 教養のある人になりたい私の読書感想文/kyouyounoaruhito
教養のある人になりたい私の読書感想文/kyouyounoaruhito


